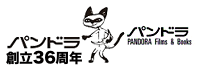| こういうのを痛快な生き様とでもいうのだろう。生きたいように気ままに生きたわけではない。それなりの蹉跌(さてつ)もあり、女としての懊悩、母としての葛藤もあった。振り返れば紆余曲折もあったけど、それでも越して来た歳月の軌跡はあざやかな足跡が深く刻まれている。そんな女一代の物語を読んだ思いだ。
もっとも本書を手にしたときは、外国語映画の属性としての「字幕」というものがどんなふうに作られているのか、現場の声に接してみようという好奇心だけだった。神島さんは、外国語映画のフィルムにスーパー字幕=文字を打ち込む技術者であり、その仕事に特化した会社を日本ではじめて興した経営者でもある。神島さんが字幕を手がけた名作は数知れない。
どんな仕事にも、その領域のみに特化する技術がある。零細企業のなかにも多くの特有の技術があって、それはみな個別化され符牒としてのことばをもつ。いわゆる業界語。そうした企業文化の総体が日本経済の成長を支えてきたのだ。そこには無数の名もない匠が生きていた。神島きみも字幕制作の匠である。映画においては黒子的存在である。そんな黒子がこうして一冊を著すのは、映画という巨きな大衆文化に関わったからである。私たちが忘れてならないのは、こうした名匠がわれわれの隣近所にも暮らしているという事実だ。その名匠の技が、映画のような華やかさを持っていないだけで、日本の工業技術を下支えしているということに気が付かねばいけない。
本書には何故、ああした〈字幕〉文字としか言いようのない特有のカタチが生まれたか? 一行の字数が決まっていて、スタンダード、ヴィスタサイズ、シネマスコープ、70ミリ映画、さらにシネラマのスクリーンに合わせて字幕を打ち込む場所や字数が違ってくる、という理由なども開陳されている。字幕打ち込みの道具とか、納期とか、著者が熟知した知識が惜しみなく提供されている。そして、著者が起こした会社から技術が伝播し、子会社、孫会社が族生していったことなども承知できる。
そうした日本の映画文化に多大な貢献をした著者もひとりの女であって、その生き様は仕事と切り離せない。
大正6年生まれというから往年の名女優・山田五十鈴さんと同じ年、トニー谷、芦田伸介、多々良純といったクセのあるアルチザンたちも大正デモクラシーの華やぎのなかで生を享けている。神島さんは東京・神田の生まれだ。筆者の祖母も神田の生まれで、その発音の歯切れの良さは、たわいない世間話を聴いているだけで、何か〈芸〉を堪能しているような趣きがあった。母は、祖母から下町ことばをそのまま受け継ぐが、神田から尾久に転居してから幼少時代をすごしたせいか、気風は希薄化されヒ音とシ音の発音が曖昧な東京弁だけが血肉化した。それを筆者は受け継いで、無意識に「シャク(百)円」と言っているらしい。
さて、神島さんの話ぶりはどのようなものだったのだろうか? 行間から立ち上がってくるのは、祖母の気風の良さのように思う。
人は誰でも時代の制約のなかでしか生きられない。神島さんも戦前・戦中・戦後のなかを生き抜いた。戦後は字幕制作の技術者として、経営者として。けれど戦前は、銀座のホステス稼業でオンナを磨いたのだ。ありていに言って色々あった、と書いて躊躇しない。天晴れであるし、戦中の息苦しさも商才と生活者の知恵で颯爽と生き抜いた、と思わせる性根の座りようも豪胆だ。だから、一作毎にノーハウを蓄積していく字幕制作に関わる事業も、書く人が書けば、涙ぐましい奮闘努力の一巻になるはずだが、神島さんの手にかかると、どこかゲーム感覚の心地よさがある。無論、数夜に及ぶ不眠の作業とか、難題に取り組む労苦は字面でわかるが、それでもなお風通しの良さを感じてしまう。字幕制作という仕事に対する関心から発し、大正生まれの天晴れなオンナの生き様を知って閉じる著書ということになるか。
1993年、神島さんには、半世紀の長い間、映画のスーパー字幕の打ち込み事業一筋に献身した労苦に報いて、と日本映画ペンクラブ賞が贈られている。文科省も監督や俳優ばかりでなく、こうした神島さんのような仕事にも目配りすべきだろう。
|