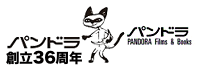| 帯にこうある〈豊かだった映画の時代/封切り館には長蛇の列が! 御期待を乞う!!〉と。その長蛇の列の尻っぽに親父の足にまとわりついて並んだ体験をもっている。
テレビが家にやってくる前の昭和の三十年代の話。何故か、親父に連れられてみた映画の記憶に日本映画はほとんどなくて、いわゆる洋画ばかりだった。で、本書を読みながら思った。日曜日、親父がいそいそと洋画を観に出向いた、その選択基準のひとつに予告篇があったに違いないと。当時、映画の宣伝媒体は新聞と雑誌、割引き券付きの折込み広告ぐらいで今と比べると露出度は極めて小さかった。そんな時代に予告篇の効用は絶大なものであったろう。予告篇制作者が思う以上に映画ファンに深甚な影響を与えていたと思う。
そう本書は、映画が庶民の“娯楽の王様”であった当時、予告篇づくりに専心していた人の回顧録である。長蛇の列をわが社、配給作品を上映する映画館前に引率すべく、奮闘努力した宣伝屋さんの苦心談でもある。作品論、監督と俳優さんを語ることで成立している大半の映画史では絶対に顧みられない裏方さんの半生記。業界で「三分間の詐欺師」と呼ばれたということだ。とすれば、親父は著者の“詐欺”に繰り返しあっていたカモであったに違いない。ふと、そんなふうに思った。
予告篇制作とは、本編を針小棒大に宣伝する行為であるだろう。愚作も“珠玉の名編”とみせる詐欺行為だ。いかがわしい。けれど、映画館の観客は「予告篇」の大言壮語をいつだって割引いてみているはずだ。それは昔も今も変わらないと思う。ただ昔はよりイベント性が高く、日常から切り離された異空間は独特の華やぎがあったはずだ。私だって、「おせんにキャラメル」と休息時間に通路を練り歩く売り子さんの呼び声を覚えている。そんな時代には、予告篇のウソは縁日の見世物小屋のろくろ首みたいなもんだ。ウソも呑み込む観客に余裕があった。本編フィルムの上にデカデカと「空前のスケール!」とか、「運命に翻弄される若き二人の愛は如何に!」といった邦文が踊れば踊るほどウソは爽快感に転調する。ウソは大きくつくほど悪意はなくなる。怒髪天を衝く、のたぐいである。
しかし、本書を読んであらためて一編の映画が抱えこんだ専門技術、その職人さんたちはいったい幾つあるのかと思った。予告篇制作などは影の仕事であって、本編ではけっして制作者の名などクレジットされない。今日でこそ、本編終了後にながながとスタッフ・キャストの名が連綿と記されていて、筆者などはうんざりしてたいてい席を立つが、かつて、そう映画全盛期にはあんな資源の無駄遣いはなかったものだ。なにか深甚な理由があるのかも知れないが、私はあんな悪習を止めてしまえとせつに思う。全世界の映画制作者は地球環境にもっと留意すべきだ。みんながジ・エンド、フィン、終、完……とフェールドアウトすれば膨大なフィルムとエネルギーが節約できる。慢性的な電力不足、電気そのものが高価な途上国の映画館はたいてい本編終了すると投写をやめてしまう。米国資本のシネコンがラテンアメリカの各都市に進出していて、そこでは本編終了後も律儀に投写をつづけるけど観客の方はさっさと席を立ってしまう。ラテン暮らしの長かった筆者であるから、その習慣は今でもつづいていて、涙腺でもゆるめていない限り席を立つ。俄然、少数派。だから、いつも可能な限り通路沿いに席を取る。そうでもしないと、律儀に電話帳のような人名リストを眺めつづける観客の前を、「ごめんなすって」と通らなければいけない。しかし、マスコミ向けの試写室での観映、これはいけない。そそくさと立ってロビーに出たりすると配給会社や宣伝会社のスタッフが怪訝な顔をする。「お気に召さなかったのかな」といういぶかしげな視線を感じて痛い。これはいけないと試写室に限り日本的慣習に従うことにしているが業腹である。とせめてパンドラのスタッフには言っておこう。
閑話休題……要するに、著者が予告篇づくりを天職と入れ込んでいた時期、本編はたいていジ・エンドで緞帳が降りたのだ。エンド・ロールの“ロール”はなかった。ジ・エンド、潔く幕、である。観客一人ひとりの胸のなかでしか残影がないというものであった。本編が残影をつくるなら、予告篇は“予影”を与える仕事だ。いわば三分のフレームで観客を“口説き落とす”事師である。観客に秋波をおくる仕事である。
1950年、フランス映画『モンパルナスの夜』が公開された。ジュリアン・デュヴィヴィエ監督、1933年の名作だが戦前、輸入されるも戦争となり連合国の映画ということで上映の機会もないままお蔵入りしていた。戦後、その予告篇を著者は制作した。当時、配給先の宣伝マンだった著者が好奇心から関わったらしい、本人のみ碑銘する“処女作”である。 以後、半世紀、本編のエッセンスを凝縮する作業をひたすら、といいたいところだが、客が入ってナンボの世界、独りよがりの芸術批評は禁じ手の切り貼り三昧、許容三分のフレームに心血をそそぐ。そこに創意工夫があり、詐欺まがいの手法もあったのだろう。 しかし、手業(てわざ)に秀でた職人さんは、自分の作品のできふでき自慢めいた話を語らないものだ。職人さんは批評しない。まず謙虚である。七面倒な作文など時間の空費と思う。著者は、たぶん「佐々木さんは映画の生き証人なんだから」とか何とか煽(おだ)てられ、本書に関わることになったのだろう。
淡々と語っている。歳月と仕事の堆積が築きあげてきた技を、そこをそれだけ取り出して書くのは至難であるから、そんなふうには書いていない。著者にとってたんなる回想も貴重な証言となっているところがいいのだ。なにげなく差し出される挿話が面白い。たとえば本書の表紙、米国の映画会社のロゴが一堂に会したビル屋上の宣伝用イルミネーションである。これは戦後間もなく連合軍の民間情報教育局が創設した組織セントラル・モーション・ピクチュア・エクスチェンジのものだ。コロンビアも20世紀フォックス、ワーナーブラザースもMGMもみんなたった一組織が掌握していた時代があった。その象徴的光景である。焼け跡いたるところに放置されている都内の一角に誕生した映画配給組織のことなどを著者は淡々と語っているわけだが、編集者はこれは面白いと感じ入り、表紙にまで活用したわけだ。
職人さんの話とはそういうものだ。プロの物書きに掛かると、読者の興味の引きそうなところにサジ加減を加えるからいけない。本書は、そんな作為はまったくなく生のまま貴重な証言が語られている。本人が「貴重」さを認識しないまま話をしているので、こっちもうっかり読み過ごしてしまうリズムがある。ということで、予告篇の話より昭和映画外史といった趣きが強い本である。「御期待を乞う!!」……著者が予告篇『第三の男』などで使ったおなじみのフレーズだが、そのまま本書を手にしようという読者へ、「御期待を乞う!!」。
|