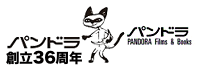| 昨年、13年ぶりに日本に帰国したわが家族を待っていたのは“韓流ブーム”であった。私が夜、書斎で仕事をはじめる頃、妻と中学生の息子が肩を並べ、「冬のソナタ」にチャンネルを合わせる日々が続いた。
妻よりグッと背の伸びた息子と妻が仲睦まじく居間に座っている光景はどことなく不安定感を誘うものだが、あえて詮索しないことにした。そんな二人の肩越しに散見する、ドラマの切れ端は、私にとってあまりにも健康食品的な映像で、中年男がとても感情移入できるものではなかった。今後も観ることはないだろう。
けれど気になった“韓流ブーム”とは如何にと。そこで密かに、‘ヨン様’源氏の『スキャンダル』を観に劇場に足を運んでみた。李朝宮廷の爛熟である。それでも色彩はおだやかで気品があった。そこで舞う美しい肢体は健康なエロスの絵巻物であった。そして、耽美な世界を射るように差し出されるキリスト教会の厳かな清涼さに、李朝衰退の兆しをみる思いがした。宮廷絵巻に刻む込む映画作家の意思に感心したものだった。
その後、『おばあちゃんの家』や『春夏秋冬そして春』、日本不在の間にヒットしたらしい『シュリ』等をみた。最近は、20歳を超えた韓国の女優さんが日本に留学してきた高校生を演じた『リンダリンダリンダ』といった映画まで試写で見るハメになった。これはもうブームというものではなくて定着であろう。
本書の著者・金さんは“韓流ブーム”の仕掛け人なのだという。1999年から2003年まで駐日韓国文化院長として在職していたあいだの努力が効を奏してブームとなったということだ。その金元院長へのロングインタビューが本書の主要構成分子である。しかし、表題にある《秘策》が包み隠さず開陳されているのか、と思って読み出すと期待を裏切られる。韓国映画の面白さを喧伝するために惜しみない努力をしたことは語られている。文部官僚として祖国の文化活動を愛し、他国へ発信したいという熱情は確かに伝わってくる。けれど《秘策》を語ることに主眼が置かれているわけではない。
一衣帯水、と日韓の距離の至近は語られても、こと文化の相互理解は海峡をつなぐ高速フェリーのように定刻化しない。ましてや、ハリウッド映画にスクリーンの寡占を赦している日本の映画環境のなかで、新興勢力が恒常的にスクリーンを確保するのは大変なことだ。
映画を針小棒大に宣伝することは可能だが、観客を騙しつづけることはできない。実際のところ《秘策》などという如意棒はこの世界には存在しない。要は、映画それ自体の面白さである。そこに芸術的価値が認められたり、商業的成功への約束、信頼があったりする。いずれにしろ映画そのものの力だ。その力を物量で圧してくるハリウッドの宣伝攻勢にどう立ち向かわせるか、それが《秘策》に関わる部分であるのかも知れない。金元院長はリアリストである。だから、自慢めいた《秘策》などはまったく語っていない。むしろ主旨からすればサブタイトルの“韓日文化交流の新時代”に込められているだろう。
しかし、13年の不在は長かった。“韓流ブーム”など夢想だにできない80年代、密かな楽しみとして今はなき池袋・西武百貨店に設けられた「スタジオ200」における韓国映画特集などに足を運んで李長鍋監督の作品に関心し、けれど周囲に語り合える同志はまことに少ないという状況に歯噛みしていた自分を思い出す。また現在の若い人には信じられないだろうが、東京にまったく奇跡のように北朝鮮映画の上映だけを試みる小さな常設館が現出したことがあった。たぶん、1年も持たず閉館したのだったが、そういうホールがかつて存在したことは記憶されるべきだろう。そう、私は当時、北と南双方で作られた『春香伝』や、韓国で人気監督となり、北に“拉致”されてメガフォンを撮ることに成る申相玉の作風の変遷はいかにと目を凝らしていたものだった。自慢ではないが、私は20年も前に、私的な“韓流ブーム”を迎えていたのだった。あまりにも時代に先行しすぎていたか……。そんなことが懐かしく思い出された本書であった。
|