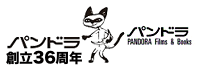|
1970年11月25日、私は朝から貨物トラックを運転して都内を走り回っていた。アルバイトの時給が当時として相当、割高な新聞配送の運転手をしていた。
1日5時間ほどで、工場の下働き労働で8時間拘束されているよりはるかに率のよい収入があった。当時、私の運転技術は水際立っていた、と思う。そういう運転に自信のあるものしか受け付けない仕事だった。新聞の束を、いかなる事情があるにせよ、1日2回、定時に出る列車に必ず乗せる。豪雨だろうが、積雪があろうが、である。少々の信号無視、追い越しなど構わない。トラックの横腹にかかれた新聞社の名は黄門様の葵の御紋のようなものだった。警察と新聞社はグルで見過ごしていた。そういう時代が確かにあったのだ。そのバイトを約1年と半歳ほどしていたが、唯一、定時の列車に間に合わなかったのが冒頭の日付けである。そう、三島由起夫が割腹自殺を謀った日である。その日、私の運転割り当ては新宿方面で、市ヶ谷付近で混雑に巻き込まれた。頭上にはヘリコプターが旋回していた。新聞社の配送口にトラックを横付けしてからはじめて三島の死を知った。
私の三島体験はそんな風にはじまった。無論、それ以前から三島作品に大いなる共感と反撥を抱きながら読んでいた。その三島が、その日、確かに胃の腑にコトンと音を立てて落ちた、と思った。
最初に読んだ三島は、新潮文庫の『仮面の告白』であったはずだ。映画『憂国』もみていたし、三島演じるチンピラヤクザがデパートのエスカレーターで憤死するB級映画もみていた。私が時間的拘束が少なく実入りの良いアルバイトを選んだのは運転技術の自信と、本を読み映画をみる時間の確保であった。
三島が死んでから少しして池袋の豊島公会堂前の公園で小さな慰霊祭が行なわれた。そこにもナントナク行った。紀伊国屋ホールで三島が生前、最後の演出として遺した芝居もみた。その出し物がなんであったか何故か想いだせない。調べればが苦もなく分かるのだろうが、それで「書評」の骨子が変わるわけではない。感興がなかったということだろう。当時、付き合っていたガールフレンドは児童劇団で着ぐるみを着て踊っていた。
三島を送別して私は三島文学から遠ざかった。正直に記せば、『豊饒の海』の連作も読んでいない。それでも全集の少ない巻が書庫の奥に仕舞い込まれている。読まないが手放せない。私にとって三島由起夫とはそういう存在か。したがって本書を批評することなどとてもできない相談だ。私的な観想を述べだけだ。けれど、そんな私にも、渡辺・三島論は大変、刺激的であった。たぶん、数多書かれた三島論のなかで〈異形〉ではないかと思う。文学論というより三島由起夫という作家を生業とした男の人間論であり、その男が宿命的に寄り添った「昭和」という時代の認知論となっている。それが綾織りしながらもつれず制御される手わざに魅了された。三島の肉体を腑分けする執刀者・渡辺も手順は、「ジェンダー・アイデンティティーとセクシュアリティ」、その懊悩と克服、挫折の道程ということになろうか。
思い出した……昭和を生きた伝統職人の生きざまを聞き書きした本のなかに、武具職人の話があって、そこにひょいと三島由起夫が出てきた。三島という作家は、そのような形で昭和の本の各所に刻印されている。その老職人がある時、「三島さんの愛用というお道具をみせて戴きました。それは見てくれだけで〈粗末〉なものでした」という箇所があった。〈粗末〉というのは無論、金銭的価値を言っているのではなく、芸術的な審美性の欠如、道具に封じ込められた技術の拙劣、濾過されていない洗練度、そうしたことを見抜けず〈自慢〉する三島という作家の軽さまで老職人は語っていたと思う。
本書のなかに石原慎太郎の言葉が引用されている。「鑑賞に耐え得る、つまり見てくれということでいえば、他のいかなるスポーツによりも、ボディービルは効率よくそれを与えてくれるだろう」と。つまり、三島が修得したという剣道もまた見てくれであって、「道」をバイバスして完成を急ぐあまり、〈心〉を落とした瑕疵が、訥弁の武具職人の言葉で喝破されていた。
そういう三島の虚構性を解き明かしたのが本書である。したがって論述は、より客観性を高めるために引用の連続的テキストとなっている。
日本でいまだ未公開でビデオにすらなっていない映画にポール・シュナイダーの『MISHIMA』がある。緒形拳が三島を演じた。その映画は象徴的に省略された無機質なセットのなかで全て撮影されていた。書割の映画。シュナイダーの三島(文学)論に相違ないが、緒形の三島はひどく滑稽感があった。実在の人物を演じて緒形がこれほど自信なさげに見えたのははじめてだと思った。
三島は戦後の昭和について言っている。「生きたとは言えない。鼻をつまんで通つたに過ぎない」と。45歳は早世ではなく、三島にとっては生きつづけてギリギリに絞り込まれた限界値であった。それはまさに「晩年」というものであった。三島が嫌った太宰治は「晩年」の諦観から小説を生業として情死するが、三島は「晩年」に身を置きながら予知された〈死〉をやんごとなく回避したのだと思った。〈死〉の誘惑から回避する身振り手振りの大仰さは彼の独創であって、それは必然、〈道〉をバイパスするホビーでしかなかった。そんなことが良く理解できる本書である。
シュナイダーの三島は、実在性もなにも在りはしなかった。木偶である。緒形の演技が自信なさげに見えたのも考えてみればシュナイダーの演出であって卓抜な批評行為であったかも知れない。
昭和の戦後を取り散らかすように書き行動し惑乱した三島由起夫という男は、彼の肉を知る妻さえ遺棄した。妻はその仕返しに、たかが知れた映画1本の公開にクレームをつけて〈夫人〉の特権を行使しつづける。彼女は、三島流の〈妻〉を演じていたに過ぎない。なめらかなウソは暴かれるまで人を傷つけない。ためらうウソは疑惑を生むが、虚言の完璧は愛情すら与える。彼女がどこまで自覚的であったかわからないが、夫が構築した〈女のいない死の楽園〉に道行きすることはないと知っていただろう。彼女は、夫の死後、そのことへ復讐している。
三島という〈男〉作家を論じて、これほど夫人の存在が希薄な作家はいない。確認していみるがいい。三島文学は家庭のぬくもりとか内助の功とか、そんな湿り気は最初からまったく存在しない。三島〈夫人〉への関心はジャーナリズムの領域にしかなく、文学の批評世界での市民権は剥奪されている。『憂国』のなかで愛妻を死の道連れにした三島だが、実在の妻には市ヶ谷での計画を一切、告げず、感づかれもしなかっただろう。関係性の冷却とかそういうものではなく、そもそも冷却の触媒となる異性愛は存在してなかった。
書評行為を逸脱した。所詮、三島は、彼が嫌った太宰の幸福を知らずに死んだ。三島の没年より、すでに10年を超えた私だが、三島の知らぬ「愛」に充足している。そんな私には三島を読むことは一種の教養行為でしかないのだろう。そして、それで充分、満足である。
|