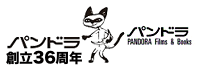|
イタリアW杯だったから1990年6月であった。僕は中米地峡諸国をおんぼろバスを乗り継いで旅をつづけていた。内戦下のエル・サルバドルの国境ゲートを通り抜け、ホンジュラスへ入った。
太陽は天頂から傾きはじめたぐらいの時間だった。夕暮れ前には首都テグシガルパに着く予定だった。ところがバスはエンジントラブルを繰り返しつづけた。スペイン植民地時代、銀鉱のあったテグシガルパは高原地帯の狭い盆地に人家が蝟集(いしゅう)する町だ。バスは気息奄々といくつもの尾根を越えて走る。到着時間はとっくに過ぎ、闇のなかをゼイゼイ言いながら転がりまろびつつ走っていた。
それが何処だったかはじめて通る場所だから見当もつかないが、いずれテグシガルパの郊外であることは間違いない。前方に広がる山陰が突然、ひかりで蠢いてみえた。明度は増し、やがてバスはそのひかりのトンネルのなかを楚々と踏み込んだ。ひかりの源は蛍だった。それも万。数万という数の蛍の群舞であった。
中米の高原地帯に棲む蛍は清水(せいすい)を必要としない。棲家も地中に穿った穴のなかであったりする。その蛍の愛の交歓、文字通りの饗宴乱舞の輝きであった。なんとも名状しがたい光景だった。宮本輝氏の『蛍川』の蛍火はワビサビの静寂なら、それはオーケストラの咆哮のような輝きであった。漆黒の闇のなかに忽然と出現した奇跡であった。文字通り言葉を失った。けれど、周囲の乗客はさして驚きもせず、運行の遅滞に苛立ち、それでも怒りもせず諦観を決め込んでいた。エアコンもない乗り合いバスの窓は全開されているからゆらぐ光は車内を徘徊しはじめる。
言葉を失ってはいたが後日、この感動をだれ彼に伝えようとするだろう、その時、なんと形容すべきかと思っていたに違いない。それを言語でなく映像で言い表せないかと思っていたようだ。そのとき、僕の脳裏に浮かんできたのは映画『炎上』の金閣寺焼亡のシーンだった。無数の金箔が木肌から剥離し炎のなかに跳ね回るようなイメージを喚起させた極彩美。あの映像をとったカメラなら山を動かす蛍の群舞を写し取れると思った。ひかりで山はうねうねとカタチを変えた。ひかりの蠢動のなかでバスは自走するのを辞(や)め、ただ神の導きのなかに吸い込まれてゆくように思った。そんな神秘的な静寂のなかで豪奢に輝く昆虫の愛の交歓を万人に伝えるのはアノ撮影者だけであるように思ったのだ。
『炎上』はモノクロームであった。けれど僕はあの炎上盛んな様に朱色や黄金の瞬きをみたと記憶している。蛍のひかりには濃淡がある。一匹一匹それぞれ明滅の速度は違うし光度も異なる。そういう万象、微細な動態のイメージを撮り得るのは宮川一夫のカメラだけであるように思った。
奇跡の邂逅は、それ以後、中米に暮らしはじめ熱帯雨林の自然を観照するフレームも宮川流であったように思う。森羅万象、である。生きた密林のなかは薄暗い。旺盛な樹冠によって光が遮られているからだ。けれど、風にゆれて樹冠に切れ間が生じると、熱帯太陽の刃は鋭く切り込んでくる。その硬度は、映画『羅生門』の暗い藪のなかに展開した人事と、その禍々しさを照射する烈しい光と同じである思った。『羅生門』もまたモノクロームのグラデーションのなかに光のプリズムを感じさせた映像であった。
〈映像を彫る〉とはうまい命名だ。〈彫る〉には職人的な業と、芸術的感性・創造力を合わせもつ。職人的撮影監督は多いけど、芸術的なひらめきを感じさせる映像作家はきわめて少ない。だから、著者は宮川世界を〈映像を彫る〉と象徴化してみせたのだろう。多くの監督が宮川カメラの恩恵で実力以上の仕事をした、と言外に強調している。
『炎上』の市川昆監督にしても、『羅生門』の黒澤明監督にしても宮川一夫という名カメラマンなくしてあの成功はなかったはずだ。映画という表現形式において撮影監督という立場は重要きわまりないが批評の序列は一段下がる。だから、監督論ほどは語られない。僕自身、本書を手にするまで撮影監督の本など読んだことはなかった。そして、本書を手にしたとき、たちまち蘇生したのが冒頭の熱帯地峡の蛍のひかりの群舞であったのだ。
丁重誠実な本だ。正直、カメラの門外漢にはスーと染み込んでこない専門用語やら機材の煩瑣がある。でも、そうした機材のことが書かれていても、結局は手工芸的な職人のぬくもりを伝えるさまざまなエピソードの紹介のなかに融解していく。幾多のエピソードがなにより面白い。『羅生門』の藪の中のシーンで強いコントラスをつくるため宮川は、「樹や草や葉などは、黒のスプレーで塗りつぶした」という。そういう裏話的エピソードが刺激的だ。カメラという工業製品を馴致させ、墨と筆、そして紙を自在に扱って倦むところのない絵師のような宮川の姿を知り、あらためて畏敬を深めた。
宮川撮影作品の目録をみると未見の作品はけっこう多いし、今後も主題からして興味の湧いてい来ない作品も多い。けれど、(名作座でみた)『羅生門』『炎上』、(公開時にみた)『沈黙』『はなれ瞽女おりん』、あるいは栗崎碧さんの作品というより宮川監督作品といったほうが正鵠を射る『曽根崎心中』……そうした一ダースばかりの名作は映像それ自体が芸術なのであった。それが生み出された現場を言葉によって再現しようという試みが本書であった。
著者・渡辺浩は松竹大船撮影所で撮影技術を習得した実作者である。いわゆる試写室通いの評論家には到底、近づくことのできないテクニカル技術を習得した者の視線がある。それは本書の力になっている。別に映画を見る目が変わるなどと有り体の褒め方はしない。けど単純に楽しみ方は倍化する。読後、すごく得したような気分になれることは請け合いだ。
|