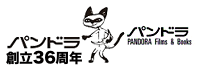『ハーヴェイ・ミルク』
藤岡朝子さんトークイベントレポート
2022年11月27日(日)
シモキタエキマエシネマK2
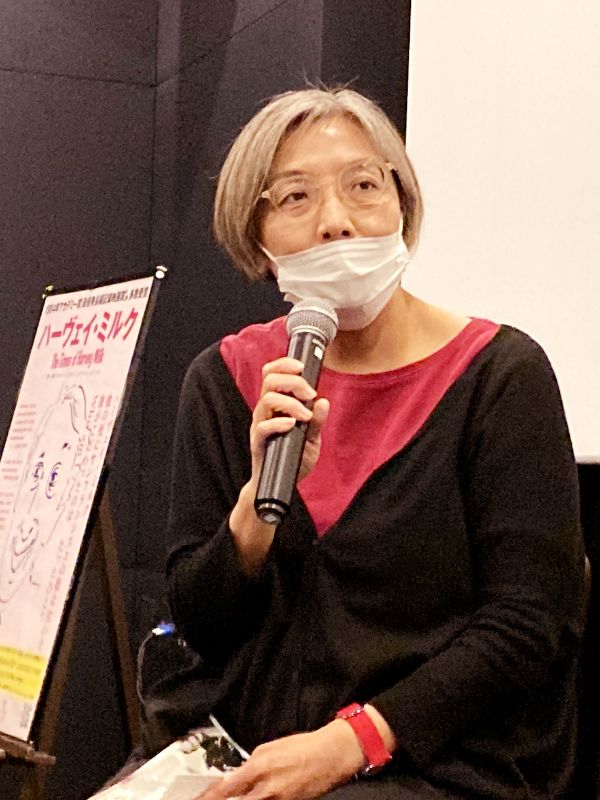
藤岡朝子さん(以下、藤岡さん): 本作は1988年に公開と中野さんからお聞きしたんですけれども、私は学生だったんですね。この映画を見に池袋のスタジオ200というスペース、映画館ではないけれども、すごく先進的なイベントをしている面白いところだったんですけど、そこに見に行ったんですね。ひとりで行ったのを覚えています。そうしたらものすごい人がごった返していて、超満員だったのにびっくりして、映画を見たら大感動して心を揺り動かされたのを覚えています。
中野 : 最初に『ハーヴェイ・ミルク』を日本で上映したときです。
藤岡 : そうだったんですね。すごく貴重な機会だったと思います。大きなスクリーンでドキュメンタリー映画を見たのは初めてだったと思います。その頃はミニシアターが始まっていたころで、シネマスクエア東急とか小さなアート系の映画をかけ始めているころだったんですよね。そういうところでヴィム・ヴェンダースの映画とかを見たりはしていたんですけれど、ドキュメンタリーの面白さというのは全然知らなかったですね。だからびっくりしました。内容と感情をすごく揺り動かされる体験だったと思います。
中野 : 映画館に上映してくれないかと頼んだのですけど、どこの映画館も内容を聞いただけでダメでしたね。相手にされなかった。
藤岡 : 内容っていうのは何のことですか?
中野 : こういうゲイの人がいて、カミングアウトしていて、あ、「カミングアウト」という言葉が当時なかったので、こういう人で、アカデミー賞をもらっている、と言ってもダメでしたね。やっとスタジオ200の担当者が5日間くらい限定で引き受けてくれました。
藤岡 : そうなんですね。そんな限られた状態だったんですね。
中野 : 評判がよかったので追加上映があって。
藤岡 : あ、私追加で行ったんだと思うな。
中野 : その年の12月にユーロスペースでも上映してくれて、それから広がっていったという感じでした。
藤岡 : さっきお聞きしたらこれがパンドラっていう会社の初配給作品だったそうで、そのところの中野さんの心づもりと言うか、一連の30年以上配給を続けていかれる中の第一作にこれを選んだのはどうしてですか?
中野 : 意図して選んだのではなくて…
藤岡 : いや、意図して選ぶでしょう、一本目は(笑)
中野 : その前の年にアメリカに行って、アメリカでこの映画のことを聞いたんです。それで偶然プロデューサーの連絡先が分かって、ニューヨークにいて、連絡したらすぐ見せてくれて、すごいよかったので、じゃあ上映しようと。
藤岡 : 会社はもうつくっていたんですか?
中野 : いや、つくってないです。
藤岡 : とにかく上映したいという気持ちだったんですね。
中野 : そうです。(アメリカに行く前は)外国映画の輸入配給会社で働いていましたので、ノウハウは少し知っていました。(結果として)これが第一回配給作品になったんです。
藤岡 : 当時、一番感動したのは、私は政治に関しては疎くて、政治にあまり関心がなかったんですけれど、見たときに、当たり前のことですが、人が自分らしく生きていくことが守られていく社会っていうこと、それをきちんと言葉にして伝えていくということが大きな輪になって、たくさんの人がそこに共感を覚えて、政治が動くというか、社会が動いていくというのを目の当たりにするような感じがしました。もちろん凶弾に倒れる悲劇とか、やはり正義が全うされないとか色んな問題があるんですが、大きく言うと、自分らしく生きるというのは素晴らしい事なんですよ、って言っている映画なので、そのことのストレートさにびっくりしました。
中野 : ストレートな映画ですよね。ストレートに意図を伝えてくれる映画ですよね。
藤岡 : ストレートにクィアなんですよね。
中野 : もう一つは編集が上手いと思いませんか?人々がハーヴェイ・ミルクに引き寄せられていくというところと、あとハーヴェイ・ミルクの表情もどんどん明るくなっていく。編集が上手いなと思いました。
藤岡 : 本当にそうですね。こういうのって、下手すると、たぶん当時は同性愛っていうとキワモノとか、イロモノみたいな扱いが多かった、今でも日本のテレビとかに出ている芸能人はそういう扱いをされることが多いけれども、そこには触れないでいくということ、編集の方針として。あと最初に事実をバンと出しちゃう。一体誰がやったんだろうかとか、犯人は誰かとか、なぜこんな事件が起こってしまったかということには全然踏み込まない、ブレない、覗き見趣味的なところに全然入っていかない、視線のまっ直ぐさというのかな、保たれていると思います。
中野 : そうですね。ハーヴェイ・ミルクの活動自体に非常にシンパシーを感じていた人たちがつくったというのが伝わってきますね。
藤岡 : この監督は、このときまだ20代なんですよね。びっくりしちゃったんですけど。今もまだ若くてずっと現役でつくり続けていて、山形国際ドキュメンタリー映画祭で上映させてもらった映画もあります。『セルロイド・クローゼット』が一番有名ですけれども。
中野 : 『セルロイド・クローゼット』をご覧になった方いらっしゃいます?アメリカの映画の中でどのように同性愛者が描かれてきたかというのを、実証的に描いたドキュメンタリーです。
藤岡 : ハリウッドの中でね。あと山形で上映した作品は、『刑法175条』でしたっけ?ナチス時代にヨーロッパではどのように同性愛者が迫害されてきたかということを伝えていく映画でした。
中野 : よくできた映画でしたね。藤岡さんはたくさんのドキュメンタリーを見ていらっしゃるでしょうが、スタジオ200に見に行こうと思ったのはなぜですか?
藤岡 : 思い出せないんですけども(笑)。今のドキュメンタリーも誰が映画を作っているかという当事者性というのが問われる時代になっていると思うんですけれども、当時から始まっていたと思うんですよね。だからパーソナルな、ポリティカルであり、アクティビストが大きなお題目を言うんじゃなくて自分自身の生き方でそれを示していく、というようなことについては感じることがあったんじゃないですかね。あまり理屈っぽくないですが、私も概念で話ができないタイプなので、そういう風に思ったんじゃないかなあ。あとはハーヴェイ・ミルクという人のビジュアルですかね。とても目が大きくて引き込まれます。カリスマ性があるっていうのかな。このチラシは、どうしてイラストのチラシをつくられたんですか?
中野 : それは簡単なことで、写真がほとんどなかったんですよ。
藤岡 : 当時は?今は色々ありますけど。
中野 : コマ撮りと言ってフィルムから抜き出すというのをするのですけど、もとが16㎜フィルムなのでそれだとぼやけてしまいますから、仕方なくてデザイナーの方に描いてもらいました。
藤岡 : でも効果的だったと思います。ちょっとユーモラスで。生真面目で一本調子というのは殺人者のダン・ホワイトがそんな感じで、この人はもっと柔らかいというか、柔和で人の心に入っていくようなタイプの人ですよね。
中野 : 魅力ですよね。藤岡さんはたくさんドキュメンタリーをご覧になっているでしょうけど、最近はLGBTQをテーマにした映画がアジアでもたくさん出てきているんじゃないですか?
藤岡 : もちろん映画もありますし、映画を生んでいく土壌の社会の変化というものもすごくありますね。山形でLGBTの当事者であったり、そうではない映画もたくさん上映してきましたけれども、けっこう早くから上映していますね。99年には台湾のミッキー・チェンの『美麗少年』とかもよく覚えています。その頃にはアメリカのバーバラ・ハマー監督を審査員でお呼びして、『ナイトレイト・キス』を中央公民館の大スクリーンで、レズビアンセックスの場面を映すということをやったりしたのはかなり自慢です。
中野 : バーバラ・ハマー監督をご存じの方いらっしゃいます?バーバラ・ハマーというのはアメリカのフィルムメーカーの女性で、ドキュメンタリーをつくっているんですが、先ほど仰いました、山形国際ドキュメンタリー映画祭の大スクリーンで、女性同士のセックスシーンを流したという大胆な人ですよね。残念ながら亡くなってしまいましたけど。
藤岡 : 今バーバラさんの自伝を読んでいるんですけれど、本当に面白くて、自分の作品づくりの経験とか、70年代のサンフランシスコのゲイ運動というか、湧いていたサンフランシスコの街のカルチャーを実際に生きてきた人なので、レズビアン・ソサエティの中の人間関係とか自分の恋愛の話とかいっぱい盛り込みながら書いている本で、対照的というのかな。ロバート・エプスタインという人がたぶん関心があったのはマスの社会の中で同性愛がどのように描かれてきたり、弾圧されてきたり、迫害されてきたかというのを暴いていって、社会の方を変えていくというドキュメンタリーの目的とか、手法だったと思うんですね。それはハーヴェイ・ミルクさんにも通じるところがあって、彼は途中から背広着て、言葉の論理と明確なマイノリティであることの誇りを武器に歩み寄っていくという姿勢だったと思うんですけど。バーバラ・ハマーの映画は非常にアーティスティックで実験映画でもあるということもありますし、人をもっと揺り動かすというか、社会全体を変えるというよりも、やはりこういう過激なものがあるべき、存在するべきじゃないか、社会には、もっとインクルーシブなあらゆる在り方が、こんな極端な在り方もあるんですよ、ということもアートを通して伝えてきた人ですよね。
中野 : 30年以上たって、だいぶ世の中も変わったと思うんですけれど、ちょっと映画から外れるんですが、未だにLGBTQに対する差別があると思うんですよ。どのようにしたら少しずつ変わっていくと思います?
藤岡 : 投票行動とかで変えていくべきだと思うんですけど。それは難しい質問で…中野さんはどう思います?
中野 : 難しいと思いますけど、35年前にこの映画を上映したときは、マスコミの人が誰も試写に来ない。大体一般的な映画でどんなに多くても10回試写をすればいいんですけど、試写室を借りていたら試写室代がかかりますから、会社でフィルムを回して35回試写をしました。今でも覚えているのは、売上がトップクラスに近い週刊誌の記者が「こういう映画があるから見てくれ」って言ったらなんて言ったと思います?「オカマの猟奇殺人ですか」って言ったんですよ。
藤岡 : そういうことですよね…
中野 : そういう時代だったんです、当時は。ですが(映画を)見るとどの人も驚いていました。変わりましたね。時間とともに映画だとか、本とか、政治もそうですけどオープンにしていくと言うんですか、そうなると変わってくることってあるんだなと思いますね。
藤岡 : そうですね。メディアの力は大きいかもしれない。それでも、これだけ今ソーシャル・メディアというか個人が発言して個人の意見が尊重されるような世の中でも、アメリカはむしろ保守化に向かっていて、日本もそういうところがあると思いますけど、キリスト教の保守的なセクターの人たちがすごく力を持っていますよね。ですから今話題になっているような女性の妊娠中絶の問題とか、社会を分断している、人間の身体の個人の選択権に関わることが問題になっていますよね。また新たな危機の時代にきている気がします。
中野 : 揺れ動いていますよね。揺れ動きながら、でも少しずつ多様性を許容する社会になっているのではないかと思いますけどね。今かなり揺れ動いていて、危険だなとは思いますけど、いかがでしょうか。
藤岡 : そうですね。先ほどお聞きしたらこの映画が世界的に、日本でもこんなに40年近く前の映画にも関わらず上映が続いている、今日もそうですけど、たくさんの人が見るようになってきていますね。
中野 : どうすればいいのか、というのは特にはないですよね。これっていうのはない。
藤岡 : LGBTQに関わらず、と言うのかな、たぶんハーヴェイ・ミルクのメッセージというのは連帯しあっていこうよということですよね。この映画ではチャイニーズのマイノリティが、サンフランシスというかカリフォルニアの中ではこんなに大きな権益というか、力を持っていたんだ、ということに気づかされます。女性の運動とか、イスラム教の人たちとか、いろんな政治や宗教や人種のマイノリティの人たちがつながって、大きな渦をつくっていくことができるという可能性を、この映画はズシンと示してくれると思いました。例えばキャンドル・ナイト、あのシーンの演出がすごくいい。誰も集まっていなかったという話から始まって、実は角を曲がったらたくさんの人が集まっていて、静かに追悼していたというところなんかは非常に感動したし、今見るとあの精神が、私たちのメディアで、例えば韓国のロウソク革命とかがありましたし、この40年の間に色々な市民運動のうねりというのが映像に捉えられて私たちの目の中に、記憶の中に刷り込まれていると思うんですけど、その一番始まりの出発点がこのミルクの時代ということかなと思います。
中野 : 色んな生き方があって当たり前だということ、それから色んな生き方をする人たちがみんな団結するというか、一緒になって動きを作るという、これは大きいですよね。
藤岡 : そうですね。あと選ぶということ。ライフスタイルという問題よりもやはりそこの境遇に生まれついたりした人が、「私はこれです」と発言できるような社会になるといいなと思います。丁度この映画を観た直後くらいに、初めて映画の字幕の仕事を何本か受けることができて、それでその中の一本がちょうど『アクトアップ』というアメリカのエイズの市民運動を捉えた、エイズ運動の最前線からの社会運動に関わる人たちを映しだしている映画の字幕をつけたりしていて。何が言いたかったかと言うと、その映画の中では最初に「私はエイズとともに生きる人間です」ということを自己宣告、自己紹介するときに言うという感動的なシーンがあって、つまり私はエイズの患者です、被害者ですというのではなくて、エイズとともに生きている人間なんですということを、私はゲイですとか私は日本人ですとか、私はイスラム教ですとかいうことにすごく似ている気がするんですよね。それをきちんと表明することができる、堂々と。アメリカっぽいと思うんですけど、そういうところから学べることはあるかなと。当時は日本にもある時代が来ていて、女性情報センターがあり、バーバラ・ハマーさんの小川プロの映画もありましたし、女性やフェミニズムとか市民運動に対してけっこう補助とか、社会的な支援とか、行政がすごくサポートした時代がありました。この映画の原題は「ハーヴェイの時代」ですよね。あの頃の日本もある種の時代、希望のある時代って感じはなかったですか。
中野:ええ、そうですね。本当にそう思います。