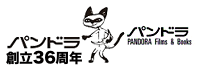『問いかける焦土』渋谷哲也さんトークイベント レポート
2022年6月18日(土)アップリンク吉祥寺にて

ヘルツォーク監督は、ドラマの撮影場所はジャングルだったり戦地だったりと、なかなか過激な場所、命の危険を感じる場所に行くことで知られています。彼は1962年から映画を発表し続けていますので、かなり活動期間が長く、その中で実はドキュメンタリー映画が半数以上を占めています。テーマも多岐に渡っていて、ドキュメンタリーを撮ったら、それを元に劇映画をつくるといったようにジャンル横断しています。この『問いかける焦土』も、解説を読んで湾岸戦争後の油田火災を鎮火する様を撮った映画だと思ってご覧になると、全く背景の説明がないので、具体的に戦争のどの段階で何が起こっているかが全く分かりません。ドキュメンタリーとして見るとちょっとあり得ない情報の少なさだと思われたかもしれません。
ヘルツォーク監督は、自分で撮りたい作品を撮る、とてもエゴの強い人だということはこの作品を見ても分かることですが、劇映画の中でも、とんでもない環境の中に俳優やスタッフチームを連れて行き、本当にサバイバルのような場面を撮ってしまいます。我々がいわば文明空間の空調の効いた中でゆったり映画を観ている、その環境を突然揺さぶって「こんな凄い世界がスクリーンの向こうにある」といつも過酷な状況を提示して、頭もリフレッシュしてくれます。
ヘルツォーク作品の自由さ
本作は『問いかける焦土』という邦題ですが、原題は“Lektionen in Finsternis”、つまり「暗黒のレッスン」という意味です。暗闇の中で何が教えられるのか、レッスン1から13までの教科書のような形になっています。最初に哲学者パスカルの言葉と銘打ってモットーが出てきます。世界の始まりではなくその崩壊の様の美しさを強調している文言ですが、パスカルの本を紐解いてもこの文章はありません。ヘルツォークが、「パスカルだったらこんなことを言うんじゃないか」と勝手に作ったそうです。そこにパスカルの署名まで入れて、映画の冒頭に置いている。こういう非常識なことをヘルツォークは平然とやります。ヘルツォークは自分で見た世界観を、映画の中にどんどん詰め込んでいってしまう。フィクション性を入れたままでドキュメンタリーも撮ってしまうという、ある種の強引さ・自由さがあります。
やはりドキュメンタリーは、現実の場所に作り手がどう関わるか、ということがあります。本作は冒頭、湾岸戦争が起こる前のクウェートの光景から第一章が始まりますが、戦争前から本作を撮影していた訳はありません。あの冒頭は、撮影に行った際、爆撃で壊れていない場所をわざと映し「戦争前でした」というナレーションを付けています。つまり、手に入れた素材を一つのドラマに加工しているわけです。
ヘルツォーク作品は、人間が生きるか死ぬか、運命により滅びるかどうか、ギリギリの限界状況に向かいます。新しい物事を発見する喜びよりも、これ以上進むと世界や自分が壊れてしまう、そのギリギリの様態に向かい合うことがヘルツォークらしいと言えます。自分を追い詰め、崩壊寸前のところまで行ってそれを見つめる、そういう世界観が作品に非常にはっきり現れていると思います。
フィクション的な距離感
ただし、自分も危機に巻き込まれて死にたいという、「死の願望」のようなものは不思議と彼の映画には感じられません。本作では炎の間近まで迫って行くわけですが、観ている我々はどういうわけか、このまま撮影チームごと焼け死ぬわけはない、地獄の業火に焼かれて終わるのではないだろうという不思議な安心感を持ちます。世界にはこんなに凄まじい、恐ろしいものがあることを見せながら、それを見ているヘルツォークはどこか達観して、冷静にまるで別次元から眺めるかのようにこの作品を提示します。ジャーナリストの仕事として現実を取材し情報として提示するのではなく、フィクションの映画監督としてドラマを作り、一つのSFのような世界観で出来事を映します。この「フィクション的な距離感」がヘルツォーク作品を考える上で重要だと思います。我々は映画を観ながら、いわば「直接暴力を受ける」感覚なしにあまりに非日常の世界にいられるのかと思います。ドキュメンタリー作品だと、観ていて実際に痛みを感じるような映画ってあるじゃないですか。そうならずに枠で守られて見るという感じがヘルツォーク作品に特徴的だと思います。これはヘルツォーク自身が、あまり過剰に被写体に感情移入しないということがあるのかもしれません。
一つ面白いのは、ヘルツォークは映像編集であまり特殊なつなぎ方をしないということです。一つ一つの映像にじっくり向かい合うスタイルが多いです。彼のインタビュー本(『ヘルツォーク・オン・ヘルツォーク』)にあったことですが、ヘルツォークは寝ている時に全く夢を見ないそうです。眠って目を閉じて、気が付いたら翌朝目が開いている、と。その間全くの「無」だそうです。つまり、ヘルツォークは「夢を見ながら自分のファンタジーが無意識の中で展開する」という経験をしていない人なのかもしれません。だからこそヘルツォークは自分の無意識の衝動を作品に投影したり、ドラマの幻想性と戯れるということがありません。カメラを持って世界を見て、その世界と直接対話しながら映像世界を作り出していく。そこが、ヘルツォーク作品の「即物的な面白さ」だと思います。ですから映っているものが本当にそのものズバリで、炎は炎、真黒な海はそれこそ本当にオイルの海です。
ただし、そこに彼の哲学や文学に対する素養が入っていて、それを神話的な次元で見せようとします。そこで意識的にメタファーを使います。本作だと、いわば別の星から来た人が砂漠の大地に着き、そこに炎と黒い海の情景があり、そして言葉の判らぬ人々が何かを語りかけてくる。それがSF的であり、実はそれがドキュメンタリーとしてその場の記録でもあります。そこにファンタジーで事物を作り替える余地がないというところが面白い点です。
「常識」を覆すヘルツォーク作品の謎
ヘルツォークは映画の中に敢えて謎めいた説明も入れます。特に12章「火のない生活」はどう思われたでしょうか。本作は1992年のベルリン映画祭に出品されました。ベルリン映画祭は、世界の三大映画祭の中では政治的、社会的テーマの映画が優遇されます。そこで戦争をテーマにしたドキュメンタリーが上映されれば、当然、様々な批評が飛び交いますが、本作はかなり批判されました。「戦争や破壊の野蛮を美的に描いている」。ということです。戦後ドイツらしい評価の観点ではあります。それはドイツ生まれのヘルツォークにとって当然予想されるべき批判だと思うんですね。実際に通常の上映では世界的に好評で、日本でもこうして問題なく観られることになっています。
そこであの「火のない生活」ですが、一旦消火した油田にもう一度火を点けていましたが、撮影のためにあの油田に火を点けてもらったのでしょうか?まさか、いくらヘルツォークでも、そこまで非常識なことをやるでしょうか。
実は本作をよく見ると分かるのですが、火を消すと、オイルが黒い雨として降り注ぎ地面に溜まり、黒い海ができます。それがどんどん広がり、まだ火が消えていない隣の油田に届くと、一面が火の海となってしまうのです。だから吹き出す原油を燃やすことによって気化させるのです。地面に溜まったオイルの海を広げないための仕方ない措置です。このように実は合理的な説明があるのですが、それを説明すると、ジャーナリストの作品になってしまうでしょう。
そこでヘルツォークは、本当に地の底から黒い泉が湧きあがってくるイメージを見せ、そこに人類の根源的要素としての火をつけるという劇的な場面を見せます。「人間には火のない生活はあり得ないのだろうか」と、戦火の中で一見見当違いのような哲学的なことをナレーションで言うわけです。そして、「作業者たちも、消火活動という仕事が失われないので安心しているのではないか」というかなり身もふたもない考察が入ります。何というか現代で無駄な仕事を重ねる社会人への皮肉なのかなと思ったりもします。
このようにヘルツォークは、普通に見ているいわゆる「理性派」、「常識派」の発想を覆すように様々な仕掛けを作品に入れ込んでいます。そこに根源的な「文明とは何か」とか、「人間社会って何だろう」という批判的考察を入れるのです。ただこの映画の方法論を完全に肯定できるかというと難しいところもあります。なんと言っても戦争の傷跡も映っているわけですし、拷問を受けて亡くなった人や身内の拷問を見なければならなかった人たちの言葉にならないインタビューもあります。拷問器具の章ですが、ドイツでは「拷問部屋で見つかったもの」というタイトルがついていますが、器具がずらっと並んでいて、ペンチ一つ映っただけでどう使用したかを考えると恐ろしいです。そのような形で人間の行為、特に悪行を淡々と即物的にヘルツォークは提示していく。それを全部含めて、この世界を丸ごと受け入れるわけです。
実はこの映画は、ポール・ベリフ(Paul Berriff)とヘルツォークが共同で撮影しました。ポール・ベリフは、英国の、どちらかというとジャーナリスト系の映像作家です。恐らく、湾岸戦争をできるだけジャーナリズム的に撮ろうとしていたと思います。ところがそこにヘルツォークが入りSF要素が加わり、一種独特のブレンドになったのだと思います。きちんと伝えるという任務と、そこに文明批判の壮大な哲学的テクストで入れ込むことが本作で成立しています。一つ一つの場面を深く見るというより、戦争や文明社会のある種の残酷さを普遍化して見る、そのような観点をもたらす作品になっていると思います。
- ポール・ベリフ(Paul Berriff)
1947年英国生まれ。45年以上のキャリアを持つ英国を代表するカメラマン。16歳で「ヨークシャー・イブニング・ポスト」紙で仕事を始め、21歳でBBC史上最年少のカメラマンに。「テレビのインディ・ジョーンズ」の愛称で知られる。BAFTAを含む合計19の業界賞を受賞。世界のテレビネットワークのドキュメンタリーを撮影する独立した制作会社を設立。ビートルズ、クイーン、ローリング・ストーンズ等著名なアーティストの撮影写真コレクションは貴重なコレクターアイテムとなっている。
子どもの視点~戦後ドイツの批判精神
ヘルツォークが、インタビューに答える女性の語った言葉を本当に訳しているのかは謎ですが、ある女性が「兵士に頭を踏まれて以来、この子は言葉を話さなくなった」と言います。子どもが「ママ、僕はもう言葉の話し方を学ばないよ」と言ったと伝えます。これらはまるで、子どもが大人の世界に対して抵抗するような痛烈な批判です。こういう批判の在り方は戦後ドイツの批判文化にかなり直結しています。ギュンター・グラスの「ブリキの太鼓」に三歳で成長を止めて子どものままで育ったオスカル・マツェラートという主人公が登場します。ギュンター・グラスは第二次大戦中まだ少年で、現在のポーランドのグダンスク(当時はドイツ領のダンツィヒ)に住んでいました。「ブリキの太鼓」は第二次大戦が勃興する有り様をオスカルという子どもの目で語った小説です。大人の世界のグロテスクさを考察することが、まさに本作の子どもの視点と重なるところがあります。戦争や、文明化が進んだことが却って「野蛮」であるという批判は、戦後ドイツでずっと行われていました。これはニュー・ジャーマン・シネマの監督のみならず、戦後ドイツの小説家にも共通しています。やはり1942年生まれのヘルツォークは、彼なりの流儀で戦後世界の批判精神の体現者であることは間違いありません。
- ギュンター・グラス(Günter Grass)
1927年10月16日~2015年4月13日。現代ドイツの作家。第二次大戦中、最年少兵士として召集され戦闘に参加し負傷して米軍の捕虜となる。この体験が後に作家としての核となる。「ブリキの太鼓」「猫と」「犬の年」の“ダンツィヒ三部作”で地位を確立。その後も「鈴蛙の呼び声」「蟹の横歩き」など問題作を次々に発表。1999年ノーベル文学賞受賞。「玉ねぎの皮をむきながら」でナチスの親衛隊員だったことを告白し、世界に衝撃が走った。小説家、劇作家、版画家、彫刻家として多彩な才能を見せた。 - 「ブリキの太鼓」
ギュンター・グラスが1959年に発表したデビュー作であり初長篇小説。第二次世界大戦後のドイツ文学における重要作品の一つ。1979年にフォルカー・シュレンドルフ(Volker Schlöndorff)により映画化され、アカデミー賞外国語映画賞、カンヌ国際映画祭パルム・ドール他多数受賞した。
「ビジョンで世界と向かい合う」
ただ一つ言えるのは、ヘルツォークは戦争の愚かさや残虐さを批判するのではなく、悪いものも良いものも全部含めて受け取る、しかも美しいものは美しいとはっきり示す。燃えている炎が美しければそのように撮る。それは「色眼鏡で善悪をつけない」視点を崩さずに、しかも批判的要素や客観的な距離感はうしないません。この微妙なバランス感覚はヘルツォークでしか味わえないものだと思います。
普通ドキュメンタリーを撮る作家は、社会的な正義というものをはっきりと作品の中に打ち出して主張するということが多い。どこかでジャーナリストの活動に近いところがあるのですが、ヘルツォークはそこからはみ出しているという点がやはり貴重だと思いますし、時にそれが危険な思想でもあるかもしれない。それも踏まえた上で、「世界って美しいものと汚いものと両方じゃないか」という当たり前のものを見られるヘルツォークの発想の自由さ、善悪や真偽という価値観を外したところで世界に向かい合うということを、皆さん味わっていってほしいと思います。
ヘルツォークが今年80歳になって未だに新作をどんどん撮り続けているというのは、よほど彼は、内省して立ち止まることなく世界に向かって目を見開き続けているということの証拠だと思います。それは若い頃も、現在80歳になってからも一貫している。けれどもその間にも世界は移り変わり、様々な相貌を見せています。この20世紀から21世紀にかけて起こる様々な戦争や自然災害をヘルツォークの目で振り返るというのは、我々にとっても発見の多い貴重な経験になるんじゃないかなと思います。