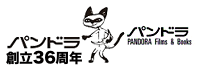7月3日(土)渋谷ユーロスペースにて13:50~『惑星ソラリス』上映終了後、
沼野充義さん(ロシア東欧文学者)によるトークイベントを行いました!
※一部抜粋してご報告致します。
 『惑星ソラリス』を見て、ある雑誌に映画評を書き、生まれて初めて原稿料を頂きました。3,000円でした。今はもうなくなっているロシア語学習雑誌ですが、編集の実質的な切り盛りをしていたのは、今は亡き米原万里(※①)さんでした。だから米原さんから原稿依頼を受けて3,000円いただいたというのが、タルコフスキーとの付き合いの始まりです。
『惑星ソラリス』を見て、ある雑誌に映画評を書き、生まれて初めて原稿料を頂きました。3,000円でした。今はもうなくなっているロシア語学習雑誌ですが、編集の実質的な切り盛りをしていたのは、今は亡き米原万里(※①)さんでした。だから米原さんから原稿依頼を受けて3,000円いただいたというのが、タルコフスキーとの付き合いの始まりです。
SFが大変好きだったので、『惑星ソラリス』も期待して見たところ、当時、日本のSFファンの間では大ブーイングが起こったことを記憶しています。つまり、SFファンが期待するようなSF映画ではなかったんですね。その頃からタルコフスキーを言わば同時代として見ているので、自分自身としても50年は経っていないと思いますが、ずっと見てきたわけです。
タルコフスキーは、間違いなく20世紀後半のソ連で最大級の映画監督の一人だと思います。個人的な好みと評価では、タルコフスキーとパラジャーノフとアレクセイ・ゲルマン(※②)、この3人が巨大な才能だと思います。他には比べようのないほど、すごい人たちだと思います。パラジャーノフはアルメニアとかコーカサスの独特の美学を持っていますからロシアからはちょっとはずれた、言わば異端ですけれども。一番正攻法的な芸術映画で、ソ連ならでは、ロシアならではの深い思索性、芸術性ということではタルコフスキーがすごいと思います。パワーにおいてはゲルマンがさらに凄まじいですが。
タルコフスキーはいつも厳しい、苦しそうな表情をしている人で、ソ連時代は検閲との闘いが本当に苦しかった。彼の日記を読むと解りますが、<タルコフスキーの受難>なんて言葉も使われるくらいです。亡命後も決して楽ではなかった。1983年から84年にかけて『ノスタルジア』をイタリアでつくり、その後亡命宣言をするのですが、すごく苦しそうな決断って感じでした。その頃から肺がんになって86年に亡くなってしまった。54歳でした。
若き日のタルコフスキー
若い頃のタルコフスキーは「時代の子」であったと思います。伝説的な<ロシア・ヌーベルヴァーグ>の代表で『僕は20歳』(マルレン・フツィエフ監督)という映画があります。これも検閲で文句を付けられ修正させられて、1965年に初めてソ連で公開された作品ですが、元々は1961年に完成していたんですね。この作品に実は若き日のタルコフスキーが出演しています。その後のタルコフスキーの真面目な「芸術映画の天才」みたいな感じからするとちょっとイメージが違う、割とチャラい若者役です。女の子に手を出そうとしたり、そういう役で出ています。タルコフスキーが生きた時代の雰囲気、ソ連の雪解け時代に、新しい文化の自由の波の中で創作を始めていたという時代の雰囲気が、よく出ていると思います。
タルコフスキーをめぐる三つの神話~反体制の神話~
タルコフスキーの生涯を振り返った場合、彼に関してある種の神話が作られていると思います。まず一つは、旧ソ連時代に彼はほとんどの映画で検閲の介入を受け、修正を余儀なくされたりして、苦しい状況の中で映画を作らざるを得なかった。だから「タルコフスキーは反体制芸術家だ」というイメージが強いと思います。実際に、タルコフスキーは『アンドレイ・ルブリョフ』についてのあるインタビューで、「こういう圧力の中で芸術家として創作するのは大変ではないですか」といった質問をされているですね。そこで彼は、「圧力なんて当たり前だ。圧力がなかったら芸術なんてできない」と、むしろ「圧力が全くない所では、本物の芸術は生まれないだろう。圧力は当たり前だ」というようなことを言っています。
こういう発言を聞くと、「反体制の神話」はタルコフスキー自身が作り上げてきたものだという感じもします。
「タルコフスキー日記」(※③)を読むと彼がいかに悩みながら映画作りに集中していたかがよくわかりますが、決して旧ソ連は人が生きていられないような、何の自由もない国ではありません。そこは誤解されないように。つまりこれだけの映画が検閲の介入があっても出来たというのは、言わば20世紀の世界の映画の遺産です。この映画が作られる状況を準備したのもソ連という国なんです。とにかくスポンサーを見つけて金にならなきゃ映画は出来ない、そういった西欧の商業映画の世界とは違いますから。『惑星ソラリス』だって巨額な予算がついているそうです。SFファンが見ると「何だこれは、あんまり科学技術っぽくなくてシャビーだな」と言う人も中にはいるんですけど、みんなが驚くくらい凄い製作費だそうです。タルコフスキーはそういう条件を与えられて映画を作ってきた。このような中で検閲と闘っていたわけですが、ソ連という国の枠の中で作るということが、西欧の映画監督と違う条件があったということです。ですから、ソ連でなければ出来なかった映画であり、ソ連体制にも関わらず出来た映画である。それが一つです。
亡命の神話
もう一つは晩年に亡命したわけですけれども、一種の<亡命の神話>というのも形作られたと思います。タルコフスキーの晩年、ソ連でペレストロイカが始まり、自由化が進みそうになっていた頃です。だから、例えばソルジェニーツィン(※④)のように、ソ連から強制的に国外退去させられたというのとは違います。タルコフスキーは潔癖なので、亡命しなくてもいいくらいだったのに亡命してしまった、と私には思えます。そういう意味で言うと、彼自身の潔癖さがこういう道を選ばせた、と思います。
純粋芸術家の神話
第三に<純粋芸術家としてのタルコフスキー>という神話があります。タルコフスキーは顔を見てもわかる通り、苦悩する人で、気難しい。完璧主義者ですから撮影の際のエピソードを聞くと、例えば草が生えているのを写すのに、気に入らない色の草が生えていると全部抜かせたとか、スモークを流した時に煙の流れ方がうまくいかないと言って、何度も何度もみんながうんざりするくらい一日かけてやった、そういったエピソードがあります。本当に細かいところで絶対に妥協しない、<純粋芸術家>という側面があります。それが西側に出てからも、西側の映画製作者との軋轢につながったと思います。
<純粋芸術家>というとまさにその通りなのですが、タルコフスキーも真空から突然現れた芸術家ではありません。やはり戦争を経たソ連のなかで、スターリンが死に、社会が自由化して若者が自由を謳歌し始めた。そのような中でタルコフスキーも若者時代にはヘミングウェイに熱中したりする、そういう普通の若者だった。そういったソ連の歴史の具体的な現実の中から出てきた人なので、決して最初から、日常の我々凡人の世界からかけ離れた、芸術の高みにいたわけではないということですね。
ここまで「反体制の神話」、「亡命の神話」、「純粋芸術家の神話」、タルコフスキーを取り巻く三つの神話があるということをお話ししましたが、そのいずれもそれなりに正しい神話、と言うとヘンですが、根拠のある神話ですけれども、あまり神話を鵜呑みにしないで鑑賞するべきなのではないかと思います。そして、彼の残した最高の遺産というのは映画以外にありませんので、まだ作品を見ていない人は是非ご覧になってください。ということで本当はスタニスワフ・レム(※⑤)との関係など『惑星ソラリス』についてもうちょっと蘊蓄を傾けたかったのですが、今日は時間がありませんので省略いたします。レムは『ソラリス』の映画化の打ち合わせでモスクワに呼ばれたのですが、タルコフスキーの映画化の方針に怒って「お前は馬鹿だ」と言い捨てて、ポーランドに帰って行ったという逸話もあります。
- 米原万里:ヨネハラ・マリ 1950年~2006年。ロシア語通訳・翻訳者/エッセイイスト。「不実な美女か貞淑な醜女か」で1994年度読売文学賞、「魔女の1ダース―正義と常識に冷や水を浴びせる13章―」で1997年講談社エッセイ賞、「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」で2002年大宅壮一ノンフィクション賞、「オリガ・モリソヴナの反語法」でBunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞している。
- アレクセイ・ゲルマン:1938年~2013年。ソ連の映画監督。日本で公開された監督作に『戦争のない20日間』(1976年)『わが友イワン・ラプチン』(1983年)『フルスタリョフ、車を!』(1998年)『神々のたそがれ』(2013年)など。
- 「タルコフスキー日記」:1991年キネマ旬報社発行の「タルコフスキー日記―殉教録」のこと。
- ソルジェニーツィン:1970年ノーベル文学賞受賞のソ連の作家アレクサンドル・イサーエヴィチ・ソルジェニーツィンのこと。1918年~2018年。1974年ソ連から追放されたがソ連崩壊後の1994年に帰国。主な著作に「イワン・デニーソヴィチの一日」 (1962年)「クレムリンへの手紙」(1974年)「収容所群島」(1973年~1975年)など。
- スタニスワフ・レム:1921年~2006年。ポーランドのSF作家。「金星応答なし」(1961年)「ソラリス」(1961年)「砂漠の惑星」(1968年)など。