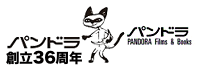6月26日(土)渋谷ユーロスペースにて13:50~『ストーカー』上映終了後、
須藤健太郎さん(映画批評家)によるトークイベントを行いました!
 『ストーカー』(1979)というとぼくはいつもクリス・マルケルの『サン・ソレイユ』(1983)のことを思い出すのですが、最近だと2018年に『ストーカー』を思い出させてくれる作品が少なくとも2本ありました。ナタリー・ポートマン主演の『アナイアレイション—全滅領域—』と鈴木卓爾監督の『ゾンからのメッセージ』です。『アナイアレイション』には〈エリアX〉という立ち入り禁止の危険地域がでてきますが、誰もが「めっちゃ〈ゾーン〉じゃん!」と思ったはずです。それから『ゾンからのメッセージ』にも〈ゾン〉というものが出てきますが、脚本を書いた古澤健さんははっきりと『ストーカー』とデニス・ホッパーの『ラストムービー』(1971)を参考にしたと言っていますから、〈ゾン〉は〈ゾーン〉から来ていたんですね。
『ストーカー』(1979)というとぼくはいつもクリス・マルケルの『サン・ソレイユ』(1983)のことを思い出すのですが、最近だと2018年に『ストーカー』を思い出させてくれる作品が少なくとも2本ありました。ナタリー・ポートマン主演の『アナイアレイション—全滅領域—』と鈴木卓爾監督の『ゾンからのメッセージ』です。『アナイアレイション』には〈エリアX〉という立ち入り禁止の危険地域がでてきますが、誰もが「めっちゃ〈ゾーン〉じゃん!」と思ったはずです。それから『ゾンからのメッセージ』にも〈ゾン〉というものが出てきますが、脚本を書いた古澤健さんははっきりと『ストーカー』とデニス・ホッパーの『ラストムービー』(1971)を参考にしたと言っていますから、〈ゾン〉は〈ゾーン〉から来ていたんですね。
ゾーンとは〈マクガフィン〉である
今日はゾーンの解釈に囚われすぎるとこの作品が見えなくなるという話を最終的にはするつもりでいますが、まずは「ゾーンとは何か」と愚直に問うことから始めてみたいと思います。タルコフスキー自身はどう説明しているか。彼も最初はわりと丁寧に解説していましたが、みんながこの質問ばかりするので晩年になるともう怒っているのか、「〈ゾーン〉なんか存在しない、これが唯一の回答だ」「ストーカーがでっちあげただけだ」といって質問を打ち切っています。でもこれは面白い答えで、とても示唆的ですね。それからこんな言い方もしています。「物語のきっかけ、3人の登場人物の人間性を探るための口実を作るもの、それが〈ゾーン〉なんだ」と。
要するにひと言で言うとゾーンとは〈マクガフィン〉だということです。〈マクガフィン〉というのはヒッチコックが有名にした言葉なので彼の説明を借りますが、たとえばスパイ映画で「機密文書を盗まなきゃいけない」というミッションがあるとすると、その機密文書がいわゆる〈マクガフィン〉と呼ばれるものです。つまり、それがあることで物語が走り出すというか、それをめぐって登場人物が動き出して、物語のきっかけを作るものですが、実はその機密文書自体に何か意味があるわけではなくて、ほかのものでもいいわけです。なので、それ自体に価値があるわけではないけれど、物語を駆動していくうえで機能的にかなめとなる役割を担っている。『ストーカー』に出てくる〈ゾーン〉は、まさにそういうものですよね。ヒッチコックは、〈マクガフィン〉は空っぽであればあるほどいい、無意味であればあるほどいいと言っていました。『北北西に進路を取れ』(1959)が成功しているのはそのためなのだ、と。
ゾーンというマクガフィンはもっと空っぽなのかもしれません。ある意味、これこそもっとも純粋なかたちのマクガフィンなのかもしれません。というのは、普通はマクガフィンは映画内のもので、映画に出てきて映画を活気づけるけれど、映画が終わってしまえば誰も気にしない。しかし『ストーカー』の場合、映画の外にもその効果や影響が及んでいて、作品が終わると、今度は登場人物の代わりに観客が「ゾーンとは何か」を探し始めるということが起こってしまうわけです。
ゾーンとは〈スクリーン〉である
さて、ゾーンとは何かというと、これは作劇的な観点からいうと〈マクガフィン〉であると言えるとして、今度はイメージの水準で考えてみるとどうでしょうか。『サン・ソレイユ』にせよ『アナイアレイション』にせよ『ゾンからのメッセージ』にせよ、〈ゾーン〉が他の作品に取り込まれていくとき、ゾーンにはかならずイメージとしての実質が与えられています。『ストーカー』ではゾーン(特にゾーン中のゾーンである「願いの叶う部屋」)は映像で示されない、不可視のものですが、後続の作品ではゾーンをイメージの問題として捉え直そう、そこにイメージとしての形態を与え直そうとする傾向があります。
スラヴォイ・ジジェク(※①)は「ゾーンとは映画の真っ白いスクリーンのことだ」と言っています。ジジェクは『ストーカー』と『惑星ソラリス』(1972)を対にして、ふたつは正反対の作品だと主張するのですが、〈ソラリス〉というのは知能を持った海のことで、人間の意識を読み取り、その人が抱いているイメージを勝手に実体化してしまう。それに対して『ストーカー』の〈ゾーン〉では願いが叶う、つまり人間はそこで思い描いたイメージを自分の意志によって実体化することができる。ただ、ジジェクはこういうふうに正反対だというわけですが、『ストーカー』でも結局は無意識が実体化されてしまうという話になるので、そういう整理をするならむしろふたつとも同じ話だと言いたくなってしまうんですけども。
ともあれ、〈ゾーン〉の中を進んでいくと、願いを叶えてくれる部屋がある。思い描いたことを実現してくれる、イメージが実現される部屋です。たしかにそれはジジェクが言うように、どんなイメージでも受け止めてしまうという意味で、あたかも「映画の真っ白いスクリーン」のようです。〈マクガフィン〉のことを作劇のゼロ度といえるとすれば、白いスクリーンは、イメージのゼロ度とでもいえるかもしれません。
解釈の彼方に
ちなみに〈ゾーン〉については解釈がたくさんあります。『ストーカー』はチェルノブイリの原発事故の前に作られていますが、事故後は〈ゾーン〉が汚染地域と重ねられ、チェルノブイリを予告した作品などと形容されることもあります。あるいは同時代的な文脈でいうなら「グラーグ」(収容所)のメタファーではないかという解釈もよく語られます。あるいはそういった社会的・歴史的な文脈を抜きにして、より普遍的なかたちで考えてみると、〈ゾーン〉とは精神世界そのものだという人もいます。奥へ奥へ進んでいくと、最終的に自分の本当の姿が啓示される、そういう秘密の空間がある、と。いまよく語られる解釈をいくつか出しましたけど、みなさんのなかにも他の解釈をしていらっしゃる方がいるのではないかと思います。〈ゾーン〉というのは、ある意味ではそうやって無限に解釈を呼ぶ「装置」なんです。
最近いろいろなきっかけが重なって、フランスの批評家セルジュ・ダネーの文章をよく読み返していましたが、彼はフランス公開当時『ストーカー』をタルコフスキーのベストだと論じていました。それはひとつにはこのストーカーというのが不法な闇ガイドで、ダネーが好きな〈パッスール〉という形象が主人公になっているからだと思うのですが、いまお話したいのはそのことではなく、『ストーカー』の魅力は解釈の彼方にあると彼がはっきり言っていることです。『ストーカー』という映画を前にすると、人々は解釈する欲望に抵抗できないが、この映画の魅力はそこに尽きるものではないと。解釈するという意識をなくしたとき、あるいはすべての解釈を終えたときいったい何が見えるだろうかとダネーは問いかけています。
タルコフスキーの映画には、いわゆる四大要素——水・火・土・風——がよく出てきますよね。タルコフスキーは水や風などをあたかも命が宿っているかのように撮ってしまう。ダネーの言葉でいうと、四大要素が「有機的な存在感」を持っている。『ストーカー』でも〈ゾーン〉に入るとなぜか炎が燃えていたりして「なんでこんなところに火があるんだ?」とひとりが言うと、ストーカーは「ここが〈ゾーン〉だからだ」と答えるわけですが、ぼくらからすれば「タルコフスキーの映画だからだ」という感じですよね。〈ゾーン〉はある意味ではタルコフスキーの映画世界を純粋培養したような世界になっていて、そこには水があり、土があり、炎があり、風があり、光がそれらを輝かせている。
それから水と土が合わさると、今度は「泥」が生まれてきます。泥は『ストーカー』にもたくさん出てくるわけですが、『アンドレイ・ルブリョフ』(1966)の主題のひとつでした。「最高の泥だ!」という印象的なセリフがありましたね。ダネーは泥のことを「形態のゼロ度」と呼んでいます。
形態のゼロ度
〈ゾーン〉の中に入ったら止まってはいけない。ストーカーはそう言っていますよね。なぜなら〈ゾーン〉は刻一刻と形を変えていくからだ、と。決まった形をとらず、時間の流れに沿ってそのつど形態を変えていくもの、たとえば水とか煙、炎もそうです。土も泥の状態になると、それこそダネーが「形態のゼロ度」といったように、形があって形がないものになっています。
『ストーカー』では水がいろんな姿になって、水の多様なバリエーションが見せられます。ところが、水には形がないとはいっても、凍ったときは固定した形態を持つじゃないかと思われるかもしれません。映画の中でも洞窟を進んでいくと氷柱が出ていて、まさにそういうことを考えさせますが、そう思った瞬間、上から水滴がぽたぽたと落ちてきて氷は溶けて形を徐々に失っていく。
ここには無限の解釈を生み出すような作劇の仕掛けが施されている一方で、解釈や意味を寄せつけない造形そのものが織りなすドラマがあります。形のあるものと形のないものが織りなす、作劇とは異なる造形のドラマが展開されている。解釈を誘う作劇と意味に回収されない造形というと、まったく異なる価値観に支えられたまったく相容れない2つのシステムのように思われますが、タルコフスキーの映画ではいつもこういう2つの異質なものが張りつめた緊張感を維持しながら保たれている。こういう緊張感の中でタルコフスキーの作品世界は成り立たせられているように思います。松本俊夫(※②)も似たようなことを言っていました。『ストーカー』の冒頭と最後で、卓上のコップが揺れている。それは夢と現実など、2つの異なる世界のはざまで磁場が作られ、それが震えとなって現れているのだ、と。
父アルセーニー・タルコフスキーの存在
まだ少しお時間があるようですので、最後にもうひと言だけお話しします。タルコフスキー映画の主人公の人物造形には似たところがあると思っていて、だいたい世間から隔絶している人物ですが、実はその人の自己犠牲によって世界そのものが成り立っている、そんな構図がありますよね。『僕の村は戦場だった』(1962)では12歳の少年というかたちをとりますが、要は芸術家のことだと思います。『ストーカー』の場合も、ストーカーはある意味ではマクガフィンを作り出すような脚本家であって、しかもその物語の中にお客さんを呼び込んで自分でそれを演出し、出演までしているので、脚本・監督・主演の完璧なアーティストですね。
タルコフスキーは自分の姿だけでなく、父アルセーニーのこともそういう主人公に重ねているように思われます。僕はタルコフスキーの映画を先に知ったので、お父さんの詩を読むと、まるでタルコフスキーの映画のようだと思ってしまうのですが、本当は逆なんですよね。タルコフスキーの映画を見ていると、ほとんどアルセーニーの詩の映像化ではないかと思われる箇所も多々あります。
『ストーカー』でも引用されていました。ジカブラスという自分の師匠にあたるストーカーがいたけど、その人の弟はゾーンに殺されたという話が出てきますが、この弟がすごくいい詩人だったといって、その詩が暗誦されます。「夏は過ぎ去った/あたかも夏が来なかったかのように/ただ陽だまりだけが残った/でもそれでは十分ではなかった」という感じですが、そのあと「でもそれでは十分ではなかった」の一節がリフレインになって何回も何回も繰り返されます。この詩がまさにアルセーニー・タルコフスキーの書いた詩です。ほかにもいい詩があるので、ぜひ読んでみてください。
※①スラヴォイ・ジジェク:スロベニアの哲学者(1949年~)。主著に『パララックス・ヴュー』(2006年)など。
※②松本俊夫:映画監督(1932年~2017年)。監督作に『薔薇の葬列』(1969年)『修羅』(1971年)など。